日本史探偵団文庫『元帥公爵大山嚴』 第六章 江川塾入門 |
|
| 久光公の上洛と随行 洋式操練の建言と江戸留學の歎願 江川塾入門 |
第六章 江川塾入門 薩英戰爭の直後、島津久光公は頻りに朝廷より召されて、國事の諮詢に應ずべく上洛することゝなり、文久三年九月十二日、城下士隊六組、外城士隊六組、此の總勢千五百餘人を率ゐ、緩急其の事に當らんとして、堂々鹿兒島を出發したが、元帥は城下士隊の一員として公に從ひ、公は陸路を取つて北上し、熊本を經て豐後に入り、二十七日鶴崎より幕府借用の汽船鯉魚丸に搭じ、二十九日兵庫に上陸し、十月朔日大阪に泊し、三日京都二本松の薩邸に到著した。 當時元帥等は、先代齊彬公の奬勵せられたる洋式操練の復舊を痛感し、且つ藩廳の當路に於ても、薩英戰爭を以て大に覺醒する所ありたるが爲、元帥等は此の機逸すべからずとして、當路に建言するに是非とも洋式を採用せらるべきを以てし、同時に江戸に留學せんことを歎願し、元帥等の先輩中原猶介も亦た之を當路に勸めた。是に於て當路も時代の要求に應じ、元帥等の建言歎願を容れ、元帥は京都の滯在四十餘日にして、十一月十六日江戸に向つて出發することゝなつた。それは江川太郞左衞門(担庵)の塾に入つて、西洋砲術を練習する爲であるが、同行の留學生は、山田孫一郞、竹内健藏、伊東次右衞門、木藤市介、林正之進、坂元兵右衞門、谷元兵右衞門、探見休藏、黑田了介と、元帥を合せて總て十人。是日椎原小彌太等の多數の見送を受けて藩邸を出で、高瀨船にて伏見に下り、伏見よりは三十石船にて淀川を下つて大阪へ、大阪よりは海路を取つて江戸に到り、元帥と山田、竹内、谷元、黑田、木藤、林の七人は、十二月三日を以て江川塾に入 |
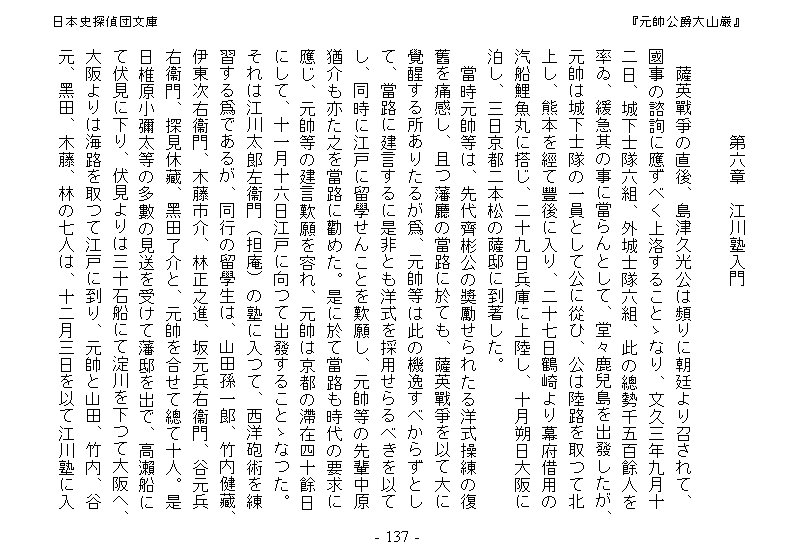 |
|
| 江川塾の由來 在塾中の状況 |
門し、八日入塾し、坂元、伊東の二人は、翌元治元年正月二日を以て入塾した。 江川太郞左衞門は慕末の傑士で、伊豆の韮山奉行として名聲あり、蘭式の兵術を高島秋帆に學びて、出藍の譽れ高く、後ち塾を江戸の芝新錢座に開いて、兵法砲術等を敎授した。新錢座の江川塾は、今の濱離宮の構内で、其の跡に只だ銀杏の樹が舊時を語つてゐるのみであつたが、其の銀杏の樹も今は枯死した。島津齊彬公の在世中、太郞左衞門は公の知遇を受けたのであるが、安政二年正月太郞左衞門の歿後、其の嗣子は韮山に居り、江戸の塾は高島秋帆及び高弟等が敎授することゝなつた。時恰も安政三年八月、齊彬公は御庭方中原猶介を拔擢して江戸留學を命じ、猶介は江川塾に入つて砲術を研究し、其の業大に進みたるが、齊彬公薨去の後、藩勢一變したるが爲、安政六年正月、一旦國に歸り、文久元年五月二十日、再び出府歸塾し、同月二十八日塾頭と爲り、諸藩の間に英名を轟かした。今元帥等の江川塾入門は、實に齊彬公以來、斯かる先輩の關係と、且は勿論時代の要求の然らしむる所とであつた。 元帥の實話に據れば(元維新史料編纂官現精華高等女學校長勝田孫彌氏への元帥の懷舊談)元帥等の入塾當時は、旗本の士大鳥圭介が塾頭で、肥田濱五郞、望月大貳等の諸士が、大鳥と共に頭角を露はしてゐた。塾生は多い時には五十人位、少い時には二十人位であつたが、いづれも諸藩から人材を選拔して入塾せしめたもので、其の他旗本の士を始とし、月に二三囘づゝ操練の講習を受くる塾外生は多數であつて、元帥等も時々諸藩邸に赴き、其の藩士の爲に訓練や兵法を敎授し |
 |
|
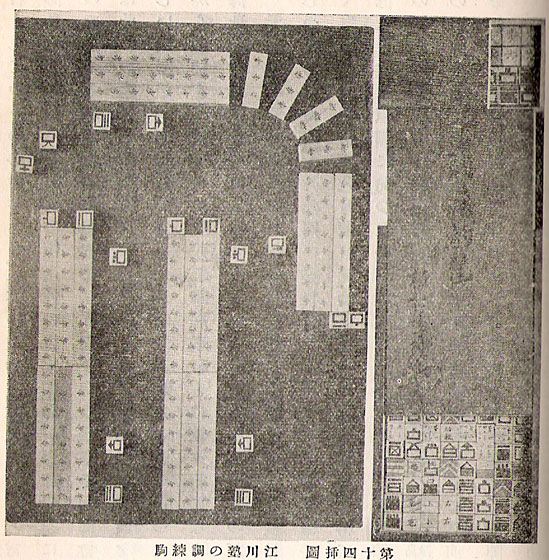 |
|
| 禁闕護衞と廣島及び蘆屋出陣 再度の出府と西鄕隆盛の惜別の一詩 |
たものであるが、我國近世の軍事は、江川塾から起つたと言つても、決して過言ではあるまい。當時勝海舟は幕府の軍艦奉行として中々の勢力があり、又其の人物も偉大であると言はれてゐたので、元帥は屢々海舟を訪問したるが、其の頃土佐の坂本龍馬が海舟の家に起居し何時も取次に出たものである、それで坂本と懇意になり、或る時は旗亭で大に會飮したこともあつた。海舟は此の坂本の取次で、常に親切に元帥等を引見し、又書面を以て特に元帥等を招き、珍らしい兵器が到來したからとて、敎示せられたこともあつた。勿論元帥等は學生であるから、服裝とても極めて粗末で、軍艦奉行とは較べ物にならなかつたのであるが、維新後海舟と會見する度毎に、當時の事を語つて大笑したものだと言ふことである。 元治元年三月二十八日、元帥は江川塾に於て目録を受け、尚ほ砲術兵學の研究を繼續しつゝあつたが、七月禁門の變後、元帥等は京都守衞を命ぜられて、江戸を出發することゝなつた。時恰も八月朔日元帥は砲術の免許皆傳を得て、同日江川塾を退き、一行二十餘人と共に京都に向つたのであるが、京都の護衞二箇月餘にして廣島に轉陣し、救應隊の名を以て廣島に到著したのが十一月八日であつた。(島津忠義公史料に據れば救應隊の人數は凡そ一千人とあり。)廣島の滯陣は僅に十四五日間にして、十一月二十一日更に筑前蘆屋の薩軍本陣に合すべき命を受けて、救應隊は同日廣島を出發したるが、蘆屋の滯陣凡そ一箇月にして解兵と爲り、慶應元年正月三日、蘆屋を引揚げて、諸隊一同は小倉より乘船歸藩の途に就き、元帥は諸隊と別れて、再び砲術研究の爲に出府し、江川塾に歸還することゝなつた。其の發するに臨み、西鄕隆盛は左の |
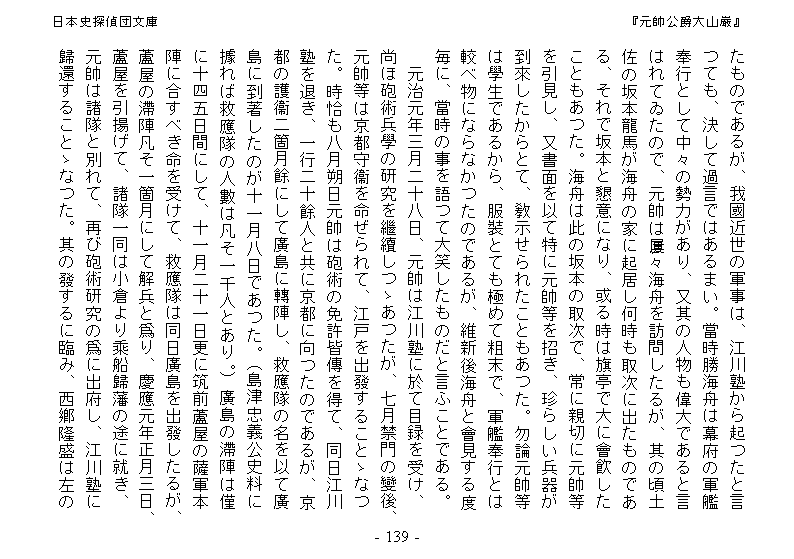 |
|
| 惜別の一詩を賦し、且つ訓誡の意を寓して贐とした。 從來素志燦交情 大義撑膓離別輕 一算投機扶百世 片言愆令斃千兵 必亡危難生疎暴 決勝竒謀發至誠 往矣愼哉雷火術 電光聲裡見輸贏 右大山士炮隊爲練磨東行賦之以代餞 南洲 西鄕と元帥とは從兄弟の間柄であるばかりでなく、夙に志を同うして、勤王大義の爲に盡瘁したるが、曩に大島より召還せられたる西鄕は、僅に二箇月にして流罪の身となり、元帥も亦た伏見寺田屋の一擧に與し、藩譴を蒙つて歸國謹愼を命ぜらるゝなど、互に流離間關相見る能はざりしに、今や征長の役、久方振りの邂逅を得て、往を談じ來を語つた事であらうが、それも廣島著後の束の間で、再び元帥が砲術研究の爲に出府することゝなつて、又も袂を分つに臨んでは、其の情の如何に切々たるものありしかは、此の一詩に於て察知するに難くはない。(世間では此詩を以て、元帥が戊辰の役砲隊長として出征するに際しての送別の辭であると言つてゐるが、それは揣摩憶測に過ぎない。)斯くて元帥は西鄕と別れて東上し、京都を經て江戸に赴き、再び江川塾の人と爲つたのは正月二十四日であつた。 × × × × |
|
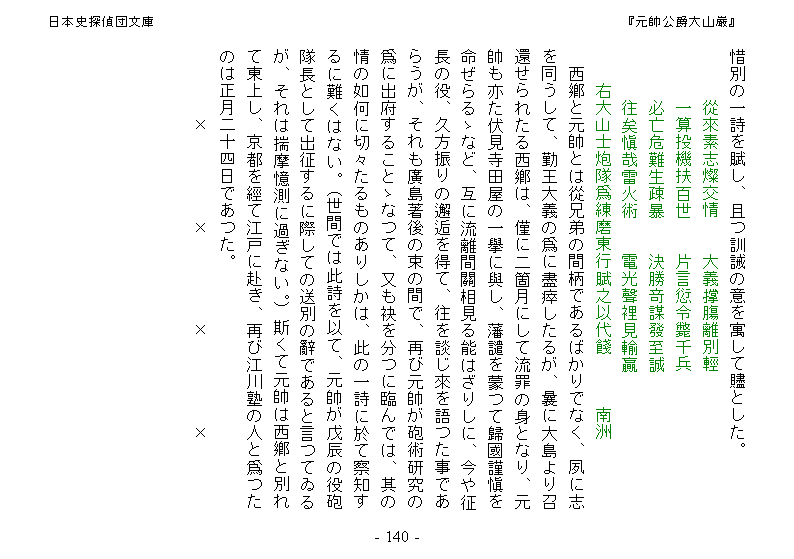 |
|
| 江川塾の公孫樹 芝新錢座の江川塾のあつた所は、今の濱離宮の一部で、其の跡に公孫樹の大木があつて、目標とせられてゐました。或る時汽車で父上と一緖に歸京の途次、汽車は品川から新橋に向ひ、濱離宮の傍を通りました。離宮の御庭に聳ゆる大公孫樹を指示しながら父上は、あれは江川太郞左衞門の塾の公孫樹であつて、俺もあの塾で學んで居つたとお話になりました。 大正三年三月十日 大山家日記 |
|
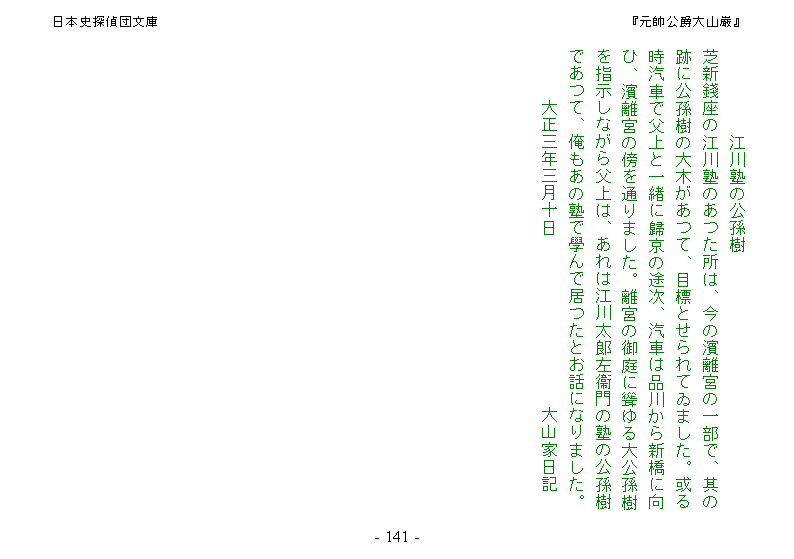 |
|